|
�g�b�v�y�[�W �� �l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ
���l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ
�@���E�Ƃ����`�ł̎��͕ʂł����A���ʂ��Ǝ��̂͋��|�̑Ώۂł͂���܂���B�ނ����т��ƌ����Ă��悢���炢�ł��B�Ȃ��Ȃ炻��͓��̂Ƃ����s���R�ȊZ����̉���ł���A�������{���̌̋��ւ̋A�҂��Ӗ����邩��ł��B�����E�Ƃ�����̃g���[�j���O��Ŋ������邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă����̂Ƃ����g���[�j���O�E�F�A�𒅂�K�v������̂ł��B�����ČÂ��Ȃ���ɗ����Ȃ��Ȃ�ΒE���̂Ă܂��B���ꂪ���Ƃ��������ɉ߂��܂���B�����������ɁA�����͓�x�Ǝ��Ԃ��̂��Ȃ���Ȋ��Ԃł���Ƃ������܂��B
�@���ʂ��Ǝ��̂͋��|�ł͂���܂���B����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͑��ɂ���܂��B����́A�u�����͂��炩���ߐݒ肵�Ă������l���v������̐��ł�������Ɖʂ������̂��v�Ƃ������Ƃł��B�����ݒ肵�Ă�������I�����̒i�K�ɂ܂ŒB���Ă��Ȃ���A�܂����܂�ς���ē��������ɑ������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł�����A�l���̒��ŋN����o�����ɂ͂ł��邾���ϋɓI�ɑΏ����Ă����K�v������܂��B���̖����N���A���邱�Ƃ���I�����̊K�i���������オ�邱�ƂɌq�����Ă�������ł��B���X�ɋN����o�����̒�����A�ł��邾�����P�����ݎ�낤�Ƃ���p������ł��B
�@�����͂��炩���ߐ��܂��O�ɐݒ肵�Ă�����������������܂��A����̐����𑣐i���邽�߂ɂ͂ǂ����Ă��K�v�ȉۑ肾�����̂�������܂���B���邢�͉������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��O������̕��̃J���}�Ȃ̂�������܂���B�����O���ł����E���Ă����Ȃ�A�����ł����E�ɒǂ����܂ꂻ���ȏ�^�����܂��B����ɑς��ꂸ���E���Ă��܂��A������܂������œ��������o���Ă��܂��̂ł��B���̈��z����E���邽�߂ɂ��A�����ӎu�ɂ���Ă��̐l���������Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@��������̒n��l���ŕ��̃J���}���`�������Ƃ��Ă��A���ꂩ��̐������ɂ���Ă�����������Ă������Ƃ͂�����x�\�ł�����A�ϋɓI�ɖ����̑P�s�ɗ�ނ��Ƃ���ł��B
�@���̃y�[�W�ł́A�l���ɍ��ꂵ�����h�ɐ����������l������A�ǂ̂悤�Ȑ��E�ɕ������ƂɂȂ�̂����O�̎���Ō��Ă����܂��B�����̎���́A�������͒n��łǂ̂悤�ɐ����Ă����悢�̂��Ƃ������{�ł���A��̗�ł�����܂��B
�g�b�v�y�[�W �� �l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ �� ����n�����C�E�l�̎���
������n�����C�E�l�̎���
 �@�w�x�[���̔ޕ��̐����x�͏\�㐢�I�㔼�����\���I�����ɂ����Đ������f�E�u�E�I�[�G���Ƃ����q�t�ɍ~�낳�ꂽ��E�ʐM�ł��B�ꊪ����l���ō\������Ă���A�ꊪ�͎�ɃI�[�G�����̕�e����̒ʐM�A�̓I�[�G�����̎��삩��A�O�A�l���͂��̎���ɏ������i���������삩��̒ʐM�Ő��藧���Ă���A�����i�ނɂ���e�����x�ɂȂ��Ă����܂��B �@�w�x�[���̔ޕ��̐����x�͏\�㐢�I�㔼�����\���I�����ɂ����Đ������f�E�u�E�I�[�G���Ƃ����q�t�ɍ~�낳�ꂽ��E�ʐM�ł��B�ꊪ����l���ō\������Ă���A�ꊪ�͎�ɃI�[�G�����̕�e����̒ʐM�A�̓I�[�G�����̎��삩��A�O�A�l���͂��̎���ɏ������i���������삩��̒ʐM�Ő��藧���Ă���A�����i�ނɂ���e�����x�ɂȂ��Ă����܂��B
�@���̏��Ђ̑�O���w�V�E�̐����ҁx�ɁA����n�����C�E�l�̎���̗l�q��`���鎟�̂悤�ȒʐM��������܂��B�ނ͂������}�Ȏ��҂ł���A��E�ł��������}�ȊK�w�Ő������n�߂Ă��܂����B
|
�@�n��̌�����������g���N���O�h�̂��ƂɂȂ邪�A�C�����ƂƂ��Ă����j���n��������Ă�����֗����B���Ƃ���炵�Ă��������̎���������݂̂ŁA���V�̔�p���x���������͈�K���c���Ă��Ȃ������B������ŏo�}�����̂��ق�̋͂��Ȓm�l�������������A�ނɂ��Ă݂�Ύ������Ƃ��g���̎҂��}���ɂ킴�킴�n��߂��܂ŗ��ē��ē������Ă��ꂽ���Ƃ����ŏ\�����ꂵ���v�����B�ē����ꂽ�����n��߂��̊K�w�̈�ŁA�����č����K�w�ł͂Ȃ������B�������������ʂ�ނ͂���Ŗ����ł������B�ƌ����̂��A��J�Ƒދ��ƕn���Ƃ̓����̂��Ƃ����ɁA�����Ɉ��炬�����������A���̊E�̋����[���i�F��ꏊ����������]�T���ł�������ł���B�ނɂƂ��Ă͂������܂��ɓV���ł���A�݂�Ȃ��e�ɂ��Ă���čK�����̂��̂������B
�iP.46�j
|
�@���̕n�����C�E�l�́A������ʓI�ȉߒ����o�ė�E�̏Z�l�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̂��Ƃ͎��������m���Ă����ׂ������ł��B�Ȃ��Ȃ�A���܂�ɂ���I�Ȓm��������������A��łȗB����`�҂ł������肷��ƁA�����������Ƃ������炸�n����̂悤�ȁg������h�ɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ肩�˂Ȃ�����ł��B�ł�����A���˂ΐ�ɗ�E���肵�Ă����e�ނ�m�l�A�y�b�g�������}���ɗ��Ă���A�ނ�ɓ�����ė�E�̗��������ׂ��Ƃ���ɗ����������ƂɂȂ�A�Ƃ������Ƃ�m���Ă����K�v������܂��B
�@��E�Ƃ͗삪�t���t���Y���Ă���悤�ȏ��ł͂Ȃ��A��������Ƃ������́E�����̂��鐢�E�ł��B�����ɂ͎R�⏬��A�X��̂悤�Ȏ��R������A����L�A�����̂悤�ȓ������������݂��Ă��܂��B����ɗ삽���̉Ƃ�����A�w�Z��a�@�A�s���@�ւȂǎЉ�@�\������A��͂��ꂼ�ꂪ�������g�̗�i��\�͂Ɍ��������d���������Ă��܂��B�����������̒n��E����E�̎ʂ��Ȃ̂ł��B�ł�����n��̂��̂���E�ɂ����Ă������s�v�c�Ȃ��Ƃł͂���܂���B�S�Ă̌��͗�E���ɂ���܂��B����Ɠ������������̖{���̏Z�݉Ƃ���E�ɂ���܂��B���͂�������̐����̂��߂ɒn��E�ւƏo�����ėl�X�ȑ̌������Ă���Œ��Ȃ̂ł��B
�@���āA���̕��}�ȌC�E�l�͗�E���肵�Ă���Ƃ�^�����A�����ł���{��ǂ�ł��܂����B���̖{�ɂ͂��̊E�ɂ͕s�ލ����̍��x�ȓ��e��������Ă���A�ǂ�ʼn��Ƃ������ł���̂ł����A�Ȃ����̂悤�Ȗ{�������̉Ƃɂ���̂��ƁA�ނ͂��Ԃ������v���Ă��܂����B���̖{�ɂ͏�w�E�ł̍��x�Ȏd���ɏA��������c�ɂ��ď�����Ă���A����ɂ��̗�c���w�����郊�[�_�[�ւ̋��P��������Ă���̂ł����B
�@���̌C�E�l�����̂悤�Ɏv���Ă����Ƃ��A�ނ̉Ƃɏ�w�E����V�g���K�˂Ă��܂����B���̓V�g�͔ނɁu����ǂ�ł���̂ł����H�v�Ɛq�˂܂��B����ɑ��C�E�l�́u�������������E�̏����̂悤�ł��B�Ȃ����̉Ƃɂ���̂�����܂���v�Ɠ����܂����B����ƓV�g���c�c
|
�@�����œV�g�͊J���Ă������̖{��j�̎肩�����ĕ��A�ق��čĂю�n�����B�����j����������ł���B�ނ͋}�ɖj��Ԃ����߂āA�Ђǂ��T�������B���̕\���ɕ����ׂĒԂ�ꂽ�����̖��O������̂ɋC�Â�������ł���B�˘f���Ȃ���ނ͂����������B
�@�u�ł����ɂ͂��ꂪ�����Ȃ������̂ł��B���̍��܂Ŏ��̖��O�������Ă���Ƃ͒m��܂���ł����v
�@�u�������A�����̒ʂ�A���Ȃ��̂��̂ł��B�ƌ������Ƃ́A���Ȃ��̕��̂��߂Ƃ������Ƃł��B�����ł����B�����͂��Ȃ��ɂƂ��Ă̓z���̈ꎞ�̋x�e���ɉ߂��Ȃ��̂ł��B�����\���x�܂ꂽ�̂ł�����A���낻�뎟�̎d���Ɏ�肩����Ȃ��Ă͂����܂���B�����ł͂���܂���B���̖{�ɏo�Ă��鍂���E�ł̎d���ł��v
�@�ނ͉����������Ƃ��������ɏo�Ȃ��B�s���̔O�ɏP���A���荞�݂��ēV�g�̑O�œ��𐂂�Ă��܂����B�����Ă���ƌ��ɏo���͎̂��̌��t�������B�u���͂����̌C�E�l�ł��B�l���w������l�Ԃł͂���܂���B���͂��̖��邢�y�n�ŕ��}�Ȑl�Ԃł��邱�ƂŖ����ł��B�����Ƃ��҂ɂ͂������V���ł��v
�iP.47-48�j
|
�@���̒j���͒n�㎞��͕n�����C�E�l�ł������A���͂ƂĂ���i�̍����삾�������Ƃ�����ŕ�����܂��B�{�l�͂���Ȃ��Ƃ͂܂������ӎ����Ă��炸�A�V�g�ɂ�����������ē��h�������Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�@�ނ̂悤�Ȃ������}�Ȑl�����A��E�̍����K�w�ɐi�߂�قǂɐi�����炵�߂��v���Ƃ͉��������̂��ɂ��āA���h���Ă���ނɑ���V�g�̎��̔�����ǂނ��Ƃŗ����ł��܂��B����͗�I�Ȑ����i��i�̌���j��ڎw���Ă��鎄�����ɂƂ��Ă��Q�l�ɂ��ׂ����ƂŁA�����ɓ��X�̐����ł̎��g�ݕ�����ł���̂��������Ă���܂��B
|
�@�u�����������t���q�ׂ���Ƃ������Ƃ����ŁA���Ȃ��ɂ͏\������̎��i������܂��B�^�̌������͏�ɗ��҂̐�ΓI�ȏ��ł���A�h�q��i�̂ЂƂȂ̂ł��B����ɂ��Ȃ��́A����ȊO�ɂ����͂ȕ�����������ł��B�����̏��͏��ɓI�Ȏ�i�ł��B���Ȃ��͂��̒n�㐶���̒��ōU���̂��߂̕�����������s���ɂ��Ă���ꂽ�B���Ƃ��ΌC����鎞���Ȃ��͂�����Ȃ�ׂ������������ĕn�����l�̍��z�̕��S���y�����Ă����悤�ƍl�����B�ׂ�����̂��Ƃ������̂��Ƃ̕����ɍl�����B��������b�g�[�ɂ��Ă���ꂽ�قǂł��B���̃��b�g�[�����Ȃ��̍��ɟ��ݍ��݁A���Ȃ��̗쐫�̈ꕔ�ƂȂ����B������ł͂��̓��͌����Ă����ɂ͈����܂���B
�@���̏゠�Ȃ��͓��X�̐�����N�����Ă���ɂ��S�炸�A���ɂ͒m�l��̎��n��A�����A�����ӂ��Ȃǂ���`���A���ɂ͕a�C�̗F�����������B���̂��߂Ɋ��������Ԃ̓��[�\�N�̖�����Ŏ��߂����B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǐ�����ɍ����Ă���ꂽ�B�����������Ƃ͂��Ȃ��̍��̋P���ɂ���ăx�[���̂����瑤���炱�Ƃ��Ƃ������Ă���܂����B�ƌ����̂��A������̐��E�ɂ́A�������̌��z���ɓV�E�̌����n�㐶�����Ƃ炵�o���A���˂��A�����͔��˂��Ȃ��Ƃ����A�������������炵���������_������̂ł��B�ł�����A�������������c�ގ҂͖��邭�Ƃ炵�o����A���Ȑ����𑗂��Ă���҂͈Â��A�C�ɉf��܂��B�i�c�㗪�c�j�v
�iP.48-49�j
|
�@�����ǂ�ŕ�����悤�ɁA��I�Ȑ����ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��͓̂��X�ɂ����Ă̑P�s�̐ςݏd�˂ł��邱�Ƃ�������܂��B�������ʂȑ傫�Ȏd�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B�����܂ł��g����̗ǐS�ɑ��Đ����ɁA�^�����ɐ�����h�Ƃ������Ƃɐs����Ǝv���܂��B�{�l�̒u����Ă�������ŁA���̐l�̏o������͈͓��ł̑P�s���d�˂Ă������Ƃ���Ȃ̂ł��B
�@�܂��A�����̕�����ǂ߂Ε�����悤�ɁA�����������𑗂��Ă���҂͓V�E����F������Ă��܂��B����ɂ��A�P��⍂���삩��A�Ȃ���x�����邱�Ƃ��ł��܂��B�t�ɁA�����ɂ܂݂ꂽ�����𑗂�҂͒ዉ�E����F������Ă���A�����ዉ��̉e�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@��̈��p��������V�g�͂��́g���Ă̌C�E�l�h�ɑ��A�u�{�ɏ�����Ă����E�ɁA���Ȃ������[�_�[�Ƃ����c������A���Ȃ��̓�����҂���тĂ���B�����A�����֎Q��܂��傤�v�Ɛ������܂��B�������ނ́u���͂��̐l������m��܂��A���ɏ]���Ă���Ȃ��ł��傤�v�ƌ����ĂȂ����a�葱���܂��B�����œV�g�́u���Ȃ��͔ނ��m���Ă���A�ނ�����Ȃ���m���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��͐������ɓ��̂��甲���o���A�ނ�Ƌ��ɌP�����Ă�������v�ƌ����A�܂��u���Ȃ������[�_�[�ɑI�̂͊ԈႢ��Ƃ����Ƃ̂Ȃ���V�g�ł���A���̑�V�g���͂ɂȂ��Ă����̂ŁA���Ȃ����撣��Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�ƌ����Đ������܂��B�����Ă��ɔނ����������邱�ƂɂȂ�܂����B��l�͍����E�ւƌ����ďo�����܂��B
|
�@���������I��ƓV�g�͔ނ��]���Ă��̉Ƃ����Ƃɂ��A�R�������ĕ���i�߁A�₪�ē����z���Ď��̊E�֍s�����B�s���قǂɔނ̈ߕ������邳�𑝂��A���n�����邭�f���A�g�̂��ǂ��ƂȂ��傫�������P�𑝂��A�R���֓o�鍠�ɂ����̎p�͂��͂₩�Ă̌C�����̂���ł͂Ȃ��A�M���q�̂���ł���A�܂��������[�_�[�炵���Ȃ��Ă����B
�@�����͒��т������y�������̂ł������B�i���т����͖̂{���̎p�����₩�Ɏ��߂����߂ł������j�����Ă��ɗ�c�̑҂Ƃ���ւ���ė����B�ЂƖڌ��Ĕނɂ͔ނ�̑S�Ă��m�F�ł����B�o�}���Ĕނ̑O�ɐ����ނ�������Ƃ��ɂ́A�ނɂ͂��łɃ��[�_�[�Ƃ��Ă̎��M���N���Ă����B�e���̖ڂɈ��̌�����������ł���B
�iP.50-51�j
|
�@�������͑��l�f����Ƃ��A���̐l�̌��Ă����Љ�I�n�ʁA�����Ă�����Y�Ȃǂf��ɂ������ł��B��������������Ō����n�����C�E�l�Ɠ�����ɐ����Ă�����A�ނ̂��Ƃ��u���}�ł܂�Ȃ��j���v�Ɣ��f������������܂���B���������̂悤�Ȕ��f�͊ԈႢ�ł��邱�Ƃ�������܂��B�Ȃ��Ȃ�ނ͂܂�Ȃ��j�ǂ��납���́u���M�ȗ�v�ł���A������c�̃��[�_�[�ł�����������ł��B�܂�������iP.104�`107�j�ł́A�n�㎞��ɔ����̘V�k�������������A���̐��ł͂��̓����̍����䂦�ɁA�����̂��Ƃ��������ƋP�����������Ƃ��ĕ`����Ă���ӏ�������܂��B���̂悤�ɁA�������͐l���������Ŕ��f���邱�Ƃ͍T����ق��������ł��B��X�p���������v��������\�������邩��ł��B
�@���̌C�E�l�̗�����Ă�������̂ł����A��E�ō����K�w�ɏ�������삪�n�㐢�E�ł͂������}�Ȑl�Ԃł��邱�Ƃ͓��ɒ��������Ƃł͂���܂���B���̃C�G�X�E�L���X�g�������̒Ⴂ�g���ł����H�̎q���Ƃ��Ēa�����Ă��܂��B�܂��A�J���}�I�Ȃ��̂Ƃ͊W�Ȃ��A�����삪���炩�̓��̓I��Q���������g�̂ɏh���Ēn��o���𑗂�ꍇ������܂��B���̏ꍇ�́A��苭�͂ȗ�I�͗ʂ��l�����邽�߂Ɏ���ɉۂ�������������ł��B����͗͂���������ł���C�s�ł�����܂��B
�@�n��E�ł͓��̓I�O�����l�Ԃ̗D��f�����̎w�W�ƂȂ肪���ł����A��I���E�ł͗�̐����x����̂̊O���I�����������߂��Ί�ɂȂ�܂��B���̐��ł͂ǂ�قǗ�I�ɔ��B�����l�ł��A���̓I�O�����D�܂����Ȃ���ΐl�Ƃ��Ẳ��l���g��h�̔��f�����ꂩ�˂܂��A���̐��ł͗�I�����x�����̂܂܊O���I�������ɔ��f�����̂ł��B�����ŏЉ���C�E�l�̏ꍇ����E�ł́u�n�����C�E�l�̊O������M���q�̂悤�Ȃ���ɕς�����v���Ƃ�������܂��B����͋t�̏ꍇ�ł������ŁA���̐��ł͔������O���������Ă����Ƃ��Ă��A��I�ɍߐ[����Η�E�ł͂��ꑊ���̏X���O���������ƂɂȂ�A���ꂪ�{�l�ɂƂ��Ă��������g�̗�I�Ȗ��n�������o����v���ɂȂ�܂��B
�@��́A��E�ł͗�i�������Ȃ�Ȃ�قǁA��������K�w�������Ȃ�Ȃ�قǁA���d�v�ʼn��l������A��肪���̂���d����^�����Ă����܂��B��E�ł͊K�w�������Ȃ�Ȃ�قǂ��̐��E�͂��������Ȃ�A�܂����傫�ȍK��������ł���悤�ɂȂ�܂��B�����͂܂��Ɍ���P�����E�ł���A�����ɏZ�ޗ삽�����܂�����P���V�g�����ł��B�ނ�͉F���̐_���m��A�P���Ԃ������͈̔͂Ɏ��߂�قǂ̑��݂ɂȂ��Ă����܂��B
�����̃y�[�W�̃g�b�v��
�g�b�v�y�[�W �� �l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ �� ���̐l���̌�� ���̐��Ŏ�����K��
�����̐l���̌�� ���̐��Ŏ�����K��
 �@���ɏЉ��́A�n��l���𗧔h�ɐ����A��E�ɋA���Ă��瑽���̍K�������Ă���삩��́A���̒n�㐢�E�ň���ꓬ���Ă��鎄�����ւ̌���̃��b�Z�[�W�ł��B�Ăсw��Ƃ̑Θb�@�V���ƒn���U�x����ł��B �@���ɏЉ��́A�n��l���𗧔h�ɐ����A��E�ɋA���Ă��瑽���̍K�������Ă���삩��́A���̒n�㐢�E�ň���ꓬ���Ă��鎄�����ւ̌���̃��b�Z�[�W�ł��B�Ăсw��Ƃ̑Θb�@�V���ƒn���U�x����ł��B
�@���҂̃A�����E�J���f�b�N�͒n��ŃT�~���G���E�t�B���b�v�Ƃ������O�ŌĂ�Ă���������삵�܂����B�J���f�b�N�͔ނ̒n��ł̐l���������̂悤�ɋL���Ă��܂��B
|
�@�T�~���G���E�t�B���b�v���́A�܂��ɑP�l�Ƃ������t�ɂӂ��킵���l���ł������B�ނ������Ӓn���Ȃ��Ƃ�����̂��������Ƃ̂���l�͈�l�����Ȃ����A�ނ��N�������̂��������Ƃ̂���l����l�����Ȃ��B
�@���́A�F�l�����ɑ��Ė{���Ɍ��g�I�ɐs�����Ă����B�����āA�K�v�ȂƂ��ɂ́A�݂�����̗��v���Ȃ������Ă܂ł��A�F�l�����ɕ�d����̂ł������B���A��J�A�]���ȂǁA�������������̂Ƃ������ɁA�l�X�ɐs�������B�������A�������R�ɁA�ɂ߂Č����ɂł���B�l�����̂��Ƃɑ��Ă���ł����������̂Ȃ�A�ނ���т����肷�邭�炢�ł������B�܂��A�ǂ�ȂɂЂǂ����Ƃ�����Ă��A�����đ�������܂Ȃ������B���m�炸�Ȏd�ł�����ƁA�u�C�̓łȂ͎̂��ł͂Ȃ��āA�ނ�̂ق��Ȃ�ł���v�ƌ����̂ł������B
�iP.27-28�j
|
�@�t�B���b�v���͌\�ŁA�����a��̖��ɖS���Ȃ�܂��B���̌�A�J���f�b�N�̎�Â������ɏ��삳��Ď��̂悤�ȃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă��܂����B
|
�u�i�c�O���c�j
�@���̐l���ɂǂ�قǑ����̎��������������́A���Ȃ��������悭�����m�̂Ƃ���ł��B�������A���肪�������ƂɁA���͌����ċt���̒��ŗE�C�������܂���ł����B���̂��ƂŖ{���Ɏ������ق߂Ă�肽���Ǝv���Ă��܂��B�����E�C���Ȃ����Ă�����A�ǂ�قǂ̂��̂������Ă����ł��傤���B�����r���ł�����߂Ă����𓊂��o���A���������āA�������Ƃ�������x�A���̓]���ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������Ƃ������c�c�B�����l���������ŁA���낵���ɐg�k������قǂł��B
�iP.27-28�j
|
�@�����̕����ɏd�v�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B���E�͘_�O�ł����A���Ƃ��V����S�������Ƃ��Ă��A�{�����̐l���̒��Ŋw�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��w���ɐl�����I���Ă��܂��ƁA������x���܂�ς���ē����ۑ�ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�n�㐢�E�i�����E�j�͗�Ƃ��Ă̎������ɂƂ��Ẵg���[�j���O��ł���Ɠ����Ɋw�Z�ł�����܂��B�ł����炱��͒n��I�Ɍ����A�u���N���Ă��܂��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�t�B���b�v���͑����܂��B
|
�@�킪�F�l���N��A�悭�悭���̐^����̓����Ă������������̂ł��B���Ȃ킿�A�w���́A����ł���K���ɂȂ�邩�ǂ������x�Ƃ������Ƃł��B�n��ɂ�����ꂵ�݂ŁA����̐����̍K�����w�i�����ȁj����Ƃ���A�����č����������ł͂���܂���B�����̎��Ԃ�O�ɂ��ẮA�n��ł̂ق�̒Z���Ԃ̋ꂵ�݂ȂǁA�{���ɉ��قǂ̂��Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�@����̎��̐l���͑����̕]���ɒl����Ƃ��Ă��A����ȑO�̐l���͂Ђǂ����̂ł����B����A�n��ňꐶ�����ɓw�͂����������ŁA�悤�₭���܂̂悤�ȋ��n�Ɏ��邱�Ƃ��ł����̂ł��B�ߋ����ł̃J���}���������邽�߂ɁA�����A�n��ɂ����Đ������̎����������蔲����K�v���������̂ł��B���͂�������������܂����B�ЂƂ��ь��ӂ�������ɂ͎㉹��f���킯�ɂ͎Q��܂���ł����B
�i�c�����c�j
�@����n��ŋꂵ�߂��l�X��A���ɂ炭������A���Ɉ��ӂ��������l�X��A���J���A���ɋ�`�����܂����l�X��A���U�ɂ���Ď��̍��Y��D���A�������R�����ɒǂ����l�X��A���͂��Ȃ������������݂̂Ȃ炸�A���Ȃ������ɐS���犴�ӂ������܂��B
�@���Ȃ������́A���Ɉ����Ȃ��Ȃ���A���͂���قǂ̑P���Ȃ��Ă����ȂǂƂ́A�Ƃ��Ă��m��ׂ����Ȃ������ł��傤�B���������Ă���K���̂قƂ�ǂ́A���Ȃ������̂������Ȃ̂ł��B���Ȃ����������Ă������������炱���A���͋������Ƃ��w�сA���ɕ�ɑP�������Ă��邱�Ƃ��w���Ă����������̂ł��B
�@�_�́A���̐i�ޓ��ɂ��Ȃ�������z���A���̔E�ϐS�������Ă����������̂ł��B�����āA�q�G��������r�Ƃ����A�ł�������̍s�ׂ��ł���悤�ɂƁA���ɋM�d�ȏC�s�̋@���^���Ă����������̂ł��B
�i�c�����c�j
�@���́A���傤�ǁA������ˑR�ƂĂ��Ȃ���Y����ɂ����n�R�l�̂悤�ȋC���ł����B���炭�̂������́A���ꂪ�{�����Ƃ͐M����ꂸ�A�����̐H���̐S�z������̂ł��B
�@�����A�n��̐l�X������̐��E��m�邱�Ƃ��ł�����A�ǂ�Ȃɂ悢���Ƃł��傤���B��������A�t���ɂ����āA�ǂ�قǂ̗E�C�A�ǂ�قǂ̗͂������邱�Ƃł��傤�B�n����_�̖@�ɑf���ɏ]�����q���������A�V���łǂ�قǂ̍K�����邩��m���Ă���A�ǂ�Ȃ��Ƃ����ĉ䖝�ł��܂��B����̐��E��m�炸�ɐ������l�́A�w�����̑Ӗ��ɂ���ēV���Ŏ������ƂɂȂ��тɔ�ׂ�A�n��ɂ��邠�����Ɏ�ɓ��ꂽ���Ă��������Ȃ��������l�̊�тȂǁA�{���ɉ��قǂ̂��Ƃ��Ȃ��x�Ƃ������Ƃ��v���m�炳����̂ł��v
�iP.30-35�j
|
�@��ڂ̉������Ɂg�_�̖@�h�Ƃ�������������܂��B���̌��t������������ƁA�����I�ȋ����ł���u�����������悤�ɗאl�������Ȃ����v�܂��́u���炪���Ăق����Ǝv�����Ƃ𑼐l�ɑ��čs���Ȃ����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������̂͂������ĒP���ŒN�ł������ł��邱�ƂȂ̂ł����A�������퐶���̒��Ŏ��H���Ă����̂͂Ȃ��Ȃ�������Ƃł��B�������A������E�ϋ������H���邱�Ƃ���I�Ȑ����ɂȂ���A����ɂ����Ă͂�荂���K�w�i�����Ă������߂̑�Ȍ��ɂȂ�̂ł��B
�@�t�B���b�v���͑O������̕��̃J���}�̉����̂��߂ɁA�����ɂ����Ă͋ꂵ���l�����g����i��Łh�I���Ƃ�������܂��B�ނɌ��炸�A�������͎���̈ӎu�ł��̐��ɂ���ė��Ă��܂��B��������芪�������ǂ�ȏł��낤�ƁA�e�ɂ͊��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���̐��ł̋M�d�ȑ̌��@���^���Ă��ꂽ����ł��B
�@�O�̃y�[�W�Łu�n��l���̖ړI�͗�Ƃ��Ă̎������g�̐�����}�邱�Ɓv�ł���Əq�ׂ܂����B�܂�g��i�̌���h�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��i�����シ�����قǗ�E�ł͂�荂���K�w�ւƐi�ނ��Ƃ��ł��܂��B�K�w�������Ȃ�Ȃ�قǁA���傫�ȍK���邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������A�����ł����̃J���}�������Ă���Ƃ��ꂪ�������܂���B������E�́g�q��Ȃ��삽���h�̐��E������ł��B��I���݂Ƃ��Ă̎������͏�ɐi�������Ă��鑶�݂ł��B�����K�w�i�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ͗�I�Ȓ���Ӗ����܂��B��ɂƂ��Ē����Ƃ������Ƃ͋�ɂȂ̂ł��B��̌��������̃J���}�̑��݂ł���ꍇ�A�ꍏ������������������悤�ƍl���܂��B���̎�i�Ƃ��āA�n��ɐ��܂�ς���ċꂵ���ꐶ����ނƂ������f�������ł��B
�@�t�B���b�v�����q�ׂĂ���悤�ɁA��Ȃ̂́u����ɍK���ɂȂ�邩�ǂ����v�Ƃ������Ƃł��B����̐����̕����n��l�������y���ɒ����̂ł��B�������n��ł̍K������ł��B�N�ɂł��K���ɂȂ錠�������邩��ł��B�ł����A�n��ł̍K���̊�~�I�Ȃ��̂ɍ��킹�Ă����ƁA����ɂ����Č�����邱�ƂɂȂ�܂��B�n��œ������Y��w���A���߂��n�ʂȂǂ͎���ɂ͎����z�����A���̐��ł͉��̈Ӗ��������Ȃ�����ł��B�����Η�E�ł͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��N����܂��B�܂�A�n��ʼn��l��M���A��������������l�����A���̐��ł͂��Ă̏��g�������Ⴂ���E�ɒu����S�߂Ȑ��������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B�����A�n�ʂ�w���A���K�邱�Ǝ��̂�������ł͂���܂���B�����͖ړI�ł͂Ȃ��A�Љ�������ł��P�����Ă����ׂ̎�i�Ƃ��ď��ɗ��p���Ă������Ƃ������Ƃ������Ƃł��B
�@�n��l���ő�Ȃ͓̂��X�ɂ�����s���ł��B�u�l�ɑ��A�܂��Љ�ɑ��Ă����Ɍ��ݓI�E�n���I�������ʂ��������v�Ƃ����n��l���ł́g�������̎��h������܂��B�����̐ςݏd�˂�����ɕ������ƂɂȂ��E�ł̈ʒu�����߂��̂ł��B���̂悤�ɁA�n��l���Ƃ����̂͂ƂĂ���Ȋ��Ԃł��B���E�Ȃ����Ă���ꍇ�ł͂���܂���B�������͂��̒n��ł̓��X�̍s���ɂ���āA��E�ł̎����̋�����n�����Ă���^���Œ��Ȃ̂ł��B���E�͐l����r���������邱�Ƃł��B����͖{���̈Ӗ��ł́g�s�k�h�ł���A�s�k�҂ɂ͂���ɑ���������E�ł̋������^�����܂��B�������ł����A���ꂪ�����Ȃ̂ł��B
�����̃y�[�W�̃g�b�v��
�g�b�v�y�[�W �� �l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ �� �S�������i�y�b�g�j�����Ƃ̍ĉ�
���S�������i�y�b�g�j�����Ƃ̍ĉ�
�@�����ŏЉ��̂͏�L���Ƃ͏����Ⴂ�A���������^�����ɒn��l���𑗂肳������Γ������тɂ��Č��Ă݂܂��B������y�b�g���������������Ƃ̂���l�ɂ͘N��ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@���łɉ��x���q�ׂĂ���Ƃ���A�������l�Ԃ͎���ł��̐�������Ɨ�E�ւƂ��̊����̏���ڂ��܂��B�ł͓��������̎���͂ǂ��Ȃ�̂��Ƃ����ƁA�ނ���܂����̂Ƃ����È߂�E���ŗ�E�ւƂ��̊����̏ꏊ���ڂ����ƂɂȂ�܂��B
�@�����炭���̐l���o�����Ă���Ǝv���܂����A�y�b�g�Ƃ̎��ʂ͂ƂĂ��h���ꂵ�����̂ł��B��������������e�Ǝ��ʂ�������h����������܂���B�����������N�����₷���l�ԓ��m�ł͂Ȃ��A�y�b�g�����Ƃ̊Ԃł͖������ň�������킵�����Ă�������ł��B�����^���A����������Ă���鑶�݂��������ƂŎ������͋ꂵ�ނ��ƂɂȂ��ł��B���̃y�b�g���X�nj�Q�ƌĂ���Ԃɂ��A���ɂ͟T��ԂɊׂ莩�E���l���Ă��܂��l������悤�ł��B
�@���̂Ƃ���A�ނ�Ƃ͕K���ĉ�ł��܂��B���������V����S�����A��E�A��ĉ�邱�Ƃ��ł���̂ł��B���̈Ӗ��Łw���̋��x�Ƃ�������͐^���ł��B�ނ瓮�������́A���Ă̎�����∤��𒍂��ł��ꂽ�l�Ԃ�Y��邱�Ƃ͂���܂���B���̐l��������ŗ�E���肷��܂ł�����̐��E�ł����Ƒ҂��Ă��Ă���܂��B
 �@�w500�ɋy�Ԃ��̐�����̌��n���x�̒��Ɏ��̂悤�ȒʐM������܂��B���̏��Ђ͎���ŊԂ��Ȃ���E�l�����ɂ���E�ʐM�ō\������Ă���A�l�Ԃ͎��㒼��ɂǂ̂悤�Ȍo�������邱�ƂɂȂ�̂����ڂ����m�邱�Ƃ��ł��܂��B�����ŏЉ�邨�b�̒ʐM��̓E�B�����b�g�Ƃ�����ŁA���㒼��ɂ��Ă̈��n�W�F�j�[�̊��}���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�w500�ɋy�Ԃ��̐�����̌��n���x�̒��Ɏ��̂悤�ȒʐM������܂��B���̏��Ђ͎���ŊԂ��Ȃ���E�l�����ɂ���E�ʐM�ō\������Ă���A�l�Ԃ͎��㒼��ɂǂ̂悤�Ȍo�������邱�ƂɂȂ�̂����ڂ����m�邱�Ƃ��ł��܂��B�����ŏЉ�邨�b�̒ʐM��̓E�B�����b�g�Ƃ�����ŁA���㒼��ɂ��Ă̈��n�W�F�j�[�̊��}���邱�ƂɂȂ�܂��B
|
�@�W�F�j�[�͎��̎O�\��O���ɔn�Ԃ������Ă��܂����B���̃W�F�j�[���N�V���Ď����A���͖{���ɔ߂��ݒQ���܂����B�W�F�j�[�͎��ɂƂ��đ��̂ǂ�ȏ��������e�������������݂ł����B���͐S���炱�̔n�������Ă��܂����B�W�F�j�[�͎��̌������Ƃ�S�ĕ������Ă���܂����B���͂���܂ł��̔n�قǂ����n�ɉ�������Ƃ�����܂���B�{���ɂ����n�ł����B
�@����������̐��E�ɗ��Ėڊo�߁A���߂ɋC���������A�n��̖쌴�̂悤�ȏ��ɂ��܂����B���ꂩ��̉��ɂ��܂����B����ƃW�F�j�[�����̕��ɗ���̂������܂����B�W�F�j�[���I�@�W�F�j�[�͎Ⴍ�����܂����B�����ĂƂĂ��K�������Ɍ����܂����B���͉��ƌ����Ă�����������܂���ł����B����͑S�������̂ł��Ȃ����Ƃł����B
�@����ɋ��������ƂɃW�F�j�[�����Ɍ�肩���Ă��܂����B�{���ɕs�v�c�ł����B���͕������܂��m���ɘb�������Ă���̂�������̂ł��i�F����͔n���b������Ȃ�Ďv�������Ȃ��ł��傤���j�B�����������������Ƃ��{���ɋN�������̂ł��B�W�F�j�[�����Ɍ�肩���A�������}���Ă���Ă���̂�������܂����B�W�F�j�[�͎��̋߂��ɗ��܂����B�����Ď��̊���Ȃ߉܂����B���͂��̎��̊������i���ɖY��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B���͂�����������قǂ��ꂵ���v���A�W�F�j�[�̑̂��y���@�������܂����B
�iP.27-28�j
|
�@���̎���̂悤�ɁA���Ƃ������ł����Ă�����������������ғ��m�ɂ́g�i���̕ʗ��h�Ƃ������̂͂���܂���B�ꎞ�I�ɕʂꂪ�����Ă��܂��Ă��A������K���ĉ�邱�Ƃ��ł��܂��B���̑Ώۂ͐l�Ԃł������ł��Ⴂ�͂���܂���B���̂��߂ɂ��������͂�������Ƃ��̐��ł̖������ʂ����Ă����˂Ȃ�܂���B
�@���̃E�B�����b�g��̂��b�ɂ͑���������̂ŁA�����̂��������������ǂ�ł݂Ă��������B
 �@�������Љ�܂��B�����ł��Љ�������P����̗�E�ʐM�ł��B�ޏ����܂��A���Ēn��Ő��������ɂ��Ă������n�Ɨ�E�ōĉ�邱�ƂɂȂ�܂��B�����A��̃E�B�����b�g��Ƃ͈Ⴄ�_������A�ޏ��̏ꍇ�͔n������ɗ�E���肷�邱�ƂɂȂ�̂ł����B �@�������Љ�܂��B�����ł��Љ�������P����̗�E�ʐM�ł��B�ޏ����܂��A���Ēn��Ő��������ɂ��Ă������n�Ɨ�E�ōĉ�邱�ƂɂȂ�܂��B�����A��̃E�B�����b�g��Ƃ͈Ⴄ�_������A�ޏ��̏ꍇ�͔n������ɗ�E���肷�邱�ƂɂȂ�̂ł����B
�@��500�N�O�A��]�Ƃ̈�l�������������i�����P�j�����B�i���͍��E���݂̐_�ސ쌧�j�r�����̎O�Y�Ƃ̒��j�̂��ƂւƉœ��肵�܂����B�����ŏ\���N�̕��Ɛ����𑗂�܂����A�����m���̂������k���Ƃ���̍U�����A�R�N���̘U�鐶���̌�A�v��Ɛb�����͓������ɂ��A������邵�Ă��܂��܂��B�ޏ����g�͗������т܂����A�邪�����Ė��N��ɖ��O�̌�ɕa�����Ă��܂��̂ł����B
�@�A�H����̏����P�́A�n��ւ̎�����g����łڂ����G�ւ̉��O�ȂǂŁA�ŏ��͔��Â����U�i���w�E�j�Ő������邱�ƂɂȂ�A�����Œn�㎞��ł̂������̕��̊����n��I���o���������Ƃ��Ă������Ƃɂ��A���������邢���U�i��w�E�j�ւƐi��ł����܂����B
�@��E�̏C�s��ŁA���鎞�ޏ������_����̏C�s�����Ă���Œ��A���n�̎ጎ�̎p�������т܂��B�����P�́u�ጎ������ł�����̐��E�ɗ����̂�������Ȃ��v�Ǝv���A�w����̂��ꂳ��Ɂu��x��킹�Ăق����v�Ɗ肢�o�܂��B�ޏ��͂��̎��̂��Ƃ����̂悤�Ɍ��܂��i���㕶�ɒ����Ă���܂��j�B
|
�@����㎄�������������Q���������ɂ��A�ጎ�͂������ɕt���Y���āA�U�X��J�����Ă���܂����B�ŁA���̗ՏI���߂Â��܂������ɂ́A���͎ጎ����Ă�Ŗ���āA���̐��̕ʂ�������܂����B�u���O�ɂ����낢�됢�b�ɂȂ�܂����c�c�B�v�S�̒��ł����v���������ł������A����͕K���n�ɂ��ʂ������Ƃł��낤�ƍl�����܂��B����قlj��������̂ł��������܂��傤�A�����≮�̓����Ő��_����̏C�s�����Ă��鎞�ɁA���鎞�v������炸�A�ጎ�̎p�����̊�ɂ͂�����Ɖf�����̂ł������܂��B
�@�u���ɂ��Ǝጎ�͂������̂����m��ʁc�c�B�v
�@���������܂����̂ŁA����l�ɂ��u�˂��Č��܂��ƁA������̐��E�Ɉ��z���ċ���Ƃ̎��ɁA���͐����ڐ̂̈��n�Ɉ����Č������Ċ���Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�u�r�i�͂Ȃ́j������Ȃ��肢�Ȃ���A��x�ጎ�̂Ƃ��֘A��čs���ĉ������ɂ͂܂���܂��܂����c�c�B�v
�@�u����͂��ƈՂ������Ƃ���B�v�Ɨ�̒ʂ肨��l�͐e�ɓ����Ă��������܂����B�u�n�̕��ł��Ђǂ����Ȃ������Ă��邩���x�͈����Ă������悢�B���ꂩ��ꏏ�ɘA��čs���ďグ��c�c�B�v
�@�H�E�ł́A�ǂ����ǂ��ʂ��Ă����̂��A�r���̂��Ƃ͖w�ǔ���܂���B�������H�E�̗��ƌ����̗��Ƃ̑傫�ȑ���_�ł������܂����A�Ƃ����������B�́A�u���Ԃɓr����ʂ蔲���āA�����̔n�̐��E�ւƂ܂���܂����B�����͌��n������n����ŁA���̓����͈������܂���B�������s�v�c�Ȃ��Ƃɂ́A�ǂ̔n���F痂����x�n����ŁA�ѕ��݂̂���������Ⴕ���A����ɋr���葾���ʔn�Ȃǂ͂ǂ��ɂ��������Ȃ��̂ł����B
�@�u���̎ጎ�������ɋ���̂�����c�c�B�v
�@�����v���Ȃ���A�ӂƌ������̖쌴�߂܂��ƁA�ꓪ�̔��n���Q��𗣂�āA��Ԃ��@���Ɏ��B�̕��삯����Ă܂���܂����B����͂����܂ł��Ȃ��A���̉��������A���n�ł������܂����B
�@�u�܂��A�ጎ�c�c���܂��A�悭���Ă��ꂽ�c�c�B�v
�@���͐S����������A������Ɏ����ɂ܂Ƃ��t�����n�̕@���A���܂ł����܂ł��y�����łĂ��܂����B���̎��̎ጎ�̂��ꂵ���Ȗʎ����c�c���͎v�킸�܂���łł��܂����̂ł������܂����B
�@���炭�n�ƈꏏ�ɗV��ŁA���͑�όy���C�����ɂȂ��Ė߂��ė��܂������A���̌��x�ƍs���Č���C�ɂ��Ȃ�܂���ł����B�l�ԂƓ����Ƃ̊Ԃ̈���ɂ͂����炩�������肵���Ƃ��낪������̂ƌ����܂��c�c�B
�iP.49-51�j
|
�@�����P�̏ꍇ���E�B�����b�g��̏ꍇ�Ɠ������A�����ɗ�E�ł��Ă̈��n�ƍĉ�ł��Ă��邱�Ƃ�����܂��B������ɏq�ׂ��悤�ɁA�ޏ��̏ꍇ�͔n������ɗ�E���肵�Ă��܂����B�ޏ��͗�E�ł̏C�s�̍Œ��ɒn��Ɏc�������n�̎���슴�ɂ���Ēm�邱�ƂɂȂ�̂ł����A���̂��Ƃ͎������̎��i��E����j�̏ꍇ�ł������ŁA��E�Ő������Ă���삽���́A�����P�̂悤�ɒn��Ɏc�����e�ޒm�l��A���Ĉ���𒍂��������̎���m�邱�Ƃ��ł��܂��B�������n��̐l�Ԃ́A���炪�����͐e�ނ�m�l���}���ɗ��Ă����Ƃ������Ƃ�m���Ă����K�v������܂��B�ނ炪���₩�ȗ�E�����ւ̏����������Ă���邩��ł��B
�@�����ŏЉ�����͔n�Ƃ̍ĉ�ł����A������̓����ł������悤�ɍĉ���ʂ������Ƃ��ł��܂��B����L�A�����Ȃǐl�ԂɂƂ��ē���ݐ[�����������ł��B�����炭���̓����A���Ƃւn���X�^�[��E�T�M�Ȃǂ̏������ł����l���Ǝv���܂��B�l�ԑ��ɂ��̓����ւ̈���������A�ނ�͂��̌̐����ێ���������ƌ����Ă��܂��B
�@���͎������l�Ԃ����̐��œ��������ƐG�ꍇ�����Ƃ͑o���ɂƂ��Ĕ��ɗL�v�Ȃ��Ƃł��B���ɓ��������ɂƂ��Ă͂��������̂Ȃ��̌��ł��B�Ȃ��Ȃ�A����������I������ڎw���Ă���̂Ɠ����悤�ɁA�ނ���܂����̐��ł̑̌��ɂ���ė�I�i����}���Ă���A�l�ԂƂ̂ӂꂠ��������𑣐i�����Ă���邩��ł��B�ł�����A������������l�͂��̐��ʼn��l�̂���d����m�炸�m�炸�̂����ɍs�Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�A��������͑o���ɂƂ��đP�����Ƃ��ĕ���邱�ƂɂȂ�܂��B���������������邱�Ƃ́A�������̐l���ɂ����Ă���ȍs�ׂł���Ӌ`�̈�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����P���Ō�Ɂu�l�ԂƓ����Ƃ̊Ԃ̈���ɂ͂����炩�������肵���Ƃ��낪������̂ƌ����܂��v�Əq�ׂĂ��܂��B�������͗�E�ł��n��ňꏏ�ɐ������Ă����y�b�g�����ƕ�炷���Ƃ͉\�ł��B�ł����l�ԂƓ����Ƃł͐i���̕��������Ⴄ�̂ŁA������ʂ�鎞�����܂��B�������A���̐��I�Ȕ߂��݂̒��ł̂���ł͂Ȃ��A���҂̔[���̏�ł̔��W�I�����ɂȂ�܂��B�ނ瓮�������́A�g�ލ��E�O���[�v�\�E���h�ƌĂ���̏W���̂Ɋ҂肻�̌��������܂����A�l�Ԃɗ^����ꂽ����ލ��S�̂̐i���𑣐i�����A�������̐l�ԂƂ��Ă̊������J�n���Ă������ƂɂȂ�܂��B

|
�f��w��ւ̋P���x�@�S�������Ƃ̍ĉ�
�v�������Q���߂��ލȃA�j�[�ɕʂ�������A����̐��E�ւƗ����N���X�B��E�̂Ƃ���ꏊ�Ŗڊo�߂��ނ́A�����ł��Ă�ނ����y�������������P�C�e�B�̊��}����B
|



�����̃y�[�W�̃g�b�v��
���@�l���̈Ӌ`�ɂ��ĂP�@���@�l���̈Ӌ`�ɂ��ĂR�@��
���g�b�v�x�[�W���͂��߂������Ƃ������E�҂����̎���P��
�����E�҂����̎���Q�����E�҂����̎���R�����E�҂����̎���S��
���l���̈Ӌ`�ɂ��ĂP���l���̈Ӌ`�ɂ��ĂQ��
���l���̈Ӌ`�ɂ��ĂR�����������Ǐ��Љ���
������Ɖ̃��O���ЂƂ�����P�̃��O��
�����A�[�J�C�u��
|

























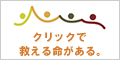
 �@�w
�@�w �@���ɏЉ��́A�n��l���𗧔h�ɐ����A��E�ɋA���Ă��瑽���̍K�������Ă���삩��́A���̒n�㐢�E�ň���ꓬ���Ă��鎄�����ւ̌���̃��b�Z�[�W�ł��B�Ăсw��Ƃ̑Θb�@�V���ƒn���U�x����ł��B
�@���ɏЉ��́A�n��l���𗧔h�ɐ����A��E�ɋA���Ă��瑽���̍K�������Ă���삩��́A���̒n�㐢�E�ň���ꓬ���Ă��鎄�����ւ̌���̃��b�Z�[�W�ł��B�Ăсw��Ƃ̑Θb�@�V���ƒn���U�x����ł��B
 �@�w
�@�w �@�������Љ�܂��B
�@�������Љ�܂��B